


ちょっとそこまで



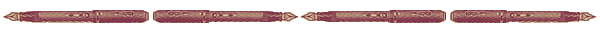 |
|
インドネシアに住んでいると、近所の人や会社の人から、「どちらへお出かけですか」と聞かれることが多い。どこへ行こうと、俺の勝手だ。なんだか、土足で、他人のプライバシーに踏み込むような感じがして、最初の頃は、どうにも好きになれなかった。「買物にどこそこのPASARまで」、「KOTAまで」とか、「今日は会社へ出かけるところです」とか、面倒だなと思いながら答えていた。 PASAR(パッサール)というのは市場(いちば)の意味だが、繁華街のブロック名に、この名前が使われている。東京で言えば、渋谷とか新宿とか言う時に、PASARという冠詞が付くと思ってもらうと良い。KOTA(コタ)というのは、町という意味である。しかし、ジャカルタでコタと言った時は、昔のバタビアの旧市街か、その旧市街にある繁華街を指している。東京で、「東京まで」と言えば、東京駅を指しているのと同じだ。 そのうち、いちいち本当のことを答える必要はないんだと思い始めて、いつも同じように「BLOCK MのPASARまで」と答えるようになった。 「BLOCK M」というのは、ジャカルタの南にあるショッピングセンター兼バスターミナルである。一番の繁華街と言っても良い。デパートやショッピングモールがある。最近は、カラオケ屋も多い。もっとも、そんな繁華街の体裁を整える前は、闇市の様相であった(闇市というのを知らない人が多いかも知れないが・・・)。テントの路地が迷路のように入り組み、わくわくしながら歩き回ったものだ。いつも、乞食の集団が、十数人は後ろに従っていた。 日本から郵便が着かない時は、この闇市まで探しに行ったもんだという話しも聞いた。日本からの手紙には、少しでも日本の雰囲気を伝えてあげようという心使いで、美しい絵葉書が選ばれる。こんな奇麗な葉書は、配達するよりも、闇市で売る方がお金になる。かくて、自分宛ての葉書が着く頃になると、自分の葉書を買い戻すために、屋台の間を歩き回ることになる。 タイプライターのリボンを1本だけ握り締めて売っている女性が居たりする。明らかに、どこかのオフィスから持ってきたものだ。しかし、その気になって探すと何でもみつかるので、とても重宝だった。 しばらくして、インドネシアの人達の会話に気づいた。誰も行き先など答えていないのだ。「どちらへお出かけですか」「ちょっと、そこまで」。そうか。これは、日常の挨拶なんだと気づいたのは、インドネシア語がだいぶ聞き取れるようになってきてからだ。以来、何の抵抗もなく、この挨拶が身についた。「どちらから」「ええ、あちらから」「これからどちらへ」「ちょっと、そこまで」「お気をつけて」「ありがとう」。 ところが、交通調査では、これが大問題なのだ。葉書による調査を諦めて、インタビュー調査を実施することにした。警察の協力を得て、ある一定のサンプル率で車を止める。そしてインタビューするわけだ。こういう国では、警官の効果は絶大である。警官が手をあげれば、必ず車は停まる。あとは、道端に寄せる誘導用の標識を用意する。面倒な準備手続きや費用は必要だが、確実にデータが得られるのは嬉しい。 集まって来たデータを見て、まずい問題が起きているのがわかった。「あっち」から「こっち」へ行くという答えがある。これでは何のことかわからない。つまり、日常会話の、「どこから来たんですか」「あちらから」「これからどちらまで」「ちょっと、そこまで」という挨拶が、そのまま調査にも反映されてしまっている。 さらに、「スラバヤから来た」「ジャカルタに行く」という答えもある。スラバヤは、ジャワ島の東の端にある町、ジャカルタは西の端だ。日本の例で言えば、銀座通りでインタビューしたら、大阪から来て東京へ行くという答えが返って来た感じだ。 すると、彼の場合は、長距離運転手かというとそうではない。「私はスラバヤが出身地です。ジャカルタの市内に向かっている。」というのが本当の意味なのだ。我々が、日本語から英語に翻訳し、英語からインドネシア語に翻訳して作った調査票では、意味のずれる部分が出てくる。言葉が示す範囲が、それぞれの言語で異なっているからだ。特に、「出発地」と「出身地」という言葉が、一定の文脈の中では正確に区別されるが、短い質問では区別できないのを知った時には本当に困った。 (*)言葉は翻訳してしまうとニュアンスが伝わらないことが多い。英語の「COOL」という言葉も、日本語だとどうなるのかと考え込んでしまう。カミュの「異邦人」も、「よそ者」の方がしっくりきそうに思えたりする。インドネシア語の「ティダアパアパ」は、「Don't mind ! 」とか「気にしない、気にしない」と訳される。しかし、そう訳してしまうと、腹を立てることになる。この話しは、またにしよう。
|
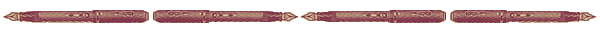 |


