


ハローバンドン



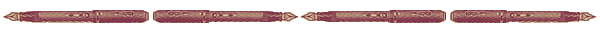 |
|
インドネシアの独立は、1945年8月16日。日本の敗戦と同時だ。連合国が上陸してくる前に、スカルノは独立宣言を読み上げた。この独立宣言の年号は、日本の皇紀で書かれている。 その後、連合国が、インドネシアを再び植民地にしようと上陸してきた。そして、インドネシアの独立戦争が始まった。当時、インドネシアに居て軍事知識を持っていたのは日本軍である。日本の名前を捨てて、インドネシアの独立に身を投じた日本人達がたくさん居た。日本の戦争の大儀名分は、アジア諸国の独立を助けることにあった。しかし、日本はアジアを植民地にしていった。だが、太平洋戦争が終わった時に、個人として、アジアの独立を助けるために自らの命を投じた人達が居る。多くの人達が亡くなって異国に眠っている。生き残った人達にも悲劇がある。日本人としては戦えないため、インドネシア国籍をとった故に、独立が達成されても、日本へ帰国できなくなってしまった人が多い。日本からは忘れ去られようとしているが、まだまだ健在で、貧困にあえいでいる人も居る。もう、本当に老齢だ。 ジャワ島の中央より西に、バンドンという町がある。世界史的には、バンドン会議で有名だ。しかし、独立戦争の時には、ここは激戦地となった。バンドンの町が陥落しようとした時、人々は、自分達の家に火を放った。連合国に何も残さないために、すべての人が、自分の大切な家、食料など何もかも、自らの手で燃やしたのだ。その立ち上る炎を見ながら、自然に歌われ始めた歌がある。「ハローバンドン」という歌だ。愛しい町、バンドンよ、我々は必ず戻ってくる。この美しい町に必ず戻って来るという歌だ。インドネシアの人なら誰でも知っている。「ハローバンドン、ハローハローバンドン」ではじまる歌を聞くと、故郷に寄せる人々の想いが伝わって来る。 このバンドンには、インドネシアでは有名なバンドン大学がある。住んでいる人達も色白で、顔は日本人と似ている(友人は、日本へ来た時に、日本人と間違えられると言っていた)。少し高地に位置しているので、別荘も多い。そんな別荘の1つに招待されたのは、インドネシアでの生活が、だいぶ長くなってからだ。 この国にも、日本と同じ、いわゆる「外人」に相当する言葉がある。この言葉(オラン・アシン)は、別の国の人というよりも、インドネシア人とは違った人達というニュアンスが強い。「彼は(彼女は)外人だからね」と話す時には、習慣を知らないんだから許してあげようかという意味が込められている。そんな愚痴を、私に向かって話されると、「私も外人だよ」と答えたくなる。でも、そんな時の答えが、「いや、あんたは外人じゃない」と言われるようになって、ようやく、どこの家でも招待してもらえるようになった。 逆に言えば、それなりに少し緊張することでもある。同国人並みに扱ってもらえる分だけ、その国の習慣に従うような注意が必要というわけだ。でも、初めて町内会へのお呼びがかかるようになった時は、とても嬉しかった。ようやく、コミュニティの一員として認めてもらえるようになった気がした。 ジャカルタからバンドンまでは、インドネシアの友達の車で、若い家族が皆で出かけた。泊まるのは、別荘。パジャマでうろうろしながら、夜中まで、枕をかかえて話し込む。話題は、どこでも同じだ。皆が考えていることは、国が違っても、そんなに変わらない。 実は、それより前に、招待してくれた若者の両親と会食したことがある。正装して出かけた。両親もインドネシアの伝統的な正装であった。食事も、食べきれないほど多くの料理が並んだ。これが習慣なのだ。お客は、料理を残して、本当に食べきれない量だったことを示す(その時は、本当に食べきれないほど多かったのだが)。食べきれないほどの料理を用意してもらった歓迎の気持ちに感謝する(似たような習慣は、日本にもある)。 私は、妻と出かけたが、妻はインドネシア語がほとんどわからない。でも、妻に対してもインドネシア語を話してから、日本語に翻訳するという手間をとった。食事が終わって、最後のお茶でほっとしていた時に、そこの御主人が取り出して来たのは、尋常小学校を優秀な成績で卒業したという卒業証書であった。そのとたん、御主人も奥さんも、素晴らしい日本語を話し始めた。おそらく、これほど正確で奇麗な日本語は、日本でも聞いたことがないと感じるような、発音も完璧な日本語だった。一瞬、冷や汗が出そうになった。もし、相手にわからないだろうと思って、日本語で、ほんの少しでも気まずい話しをしていたら、絶対に日本語が話せることを見せなかっただろう。それから、庭へ出て、趣味の盆栽を見せてもらった。この盆栽も、見事としか言いようがないものであった。 かくて、私は外人扱いから、少しは内側に入れてもらえたのだと思っている。 東南アジアでは、内緒話しを日本語でするのは、やめた方が良い。冷や汗が出そうになった経験は何度もある。 逆に、私が旅先で、日本人から「どうして日本語が上手なんですか」と聞かれた時には、「父が日本人ですから」と答えるようにしている(嘘ではない)。 町でも、同国人並みに扱われるようになると値段が変化する。英語を話す人が買物をすると、値段が高い。日本語だと、もっと高くなる。外人でも、インドネシア語を話すと、ぐっと安くなる。さらに、雑談する関係になると(高級デパートでも、皆、べちゃくちゃおしゃべりが大好きだ)、買物の値段は、交渉などしなくても現地価格になっている。 しかし、逆に問題も生じる。お金がある人が貧しい人から買う時は、高い値段でも言い値で買うのが良いと思われているからだ。寄付も要求される。ただ、本当にお金がなければ、問題はない。しかし、長く付き合っていれば、誰でも相手の懐具合なんてわかってしまう。なんとなく、古い日本の伝統が、生きている感じがする。しかし、最近は、定価販売が増えて、人情味のない都会になりつつあるかのようで残念だ。 バンドンには、露天風呂の温泉がある。皆、水着を着ているが、広い温泉だ。温泉公園とでも言った方が感じが近いかも知れない。そんな温泉につかって、美味しいサテでも食べて、うまい果物を食べていれば、ここに住むのも悪くないなぁという気になってくるだろう。 ジャカルタとバンドンの途中には、ボゴールという町があり、大きな植物公園がある。植物公園には、人の背丈くらいありそうな巨大な蝙蝠がたくさん居たのだが、数年前に行った時にはみつからなかった。ボゴールからバンドンへは、プンチャックと呼ばれる峠を越える。この峠道には、段々畑になった茶畑が見られる。ふと日本の雰囲気を思い出したくなった時には、お茶でもしに出かけると良い。以前、1~2mのバナナをみつけてびっくりしたことがあるが、馬の食べ物で、人間にはかたくて食べられないと言われた。昔は、この峠道を車で越えたが、今は、快適な高速道路もあれば、通勤列車も整備されている。
(BANDUNG)  
|
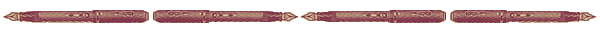 |


