


砦の上に



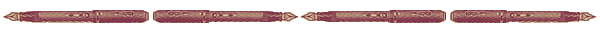 |
|
こういう話しを書くようになったら、完全なオジサンだろうなぁ。あの時、何がどういう風に進んで行ったのか、もう前後関係すら忘れつつある。学生時代は「枯れ葉の散る窓辺」ではなく小石の降る公園であったし、「重いカバンを抱え」たのじゃなくて重い○材を抱えた材木屋だった。 1月のあの日の朝。砦の上には、旗がひるがえっていた。砦を守る人達を残して、入り口は内側から封鎖された。建物の上には、最後まで残る仲間達が手をふっていた。表通りは、青い服で次第に閉鎖されつつあった。 以前の神田での頃とは、情勢が違ってきている。都電の敷石をはがしてバリケードを築き、神田の町全体を砦にした頃は、まだ多くの支持が得られていた。しかし、10月の最後の日は、逃げるしかなかった。国会前から赤坂の町へ逃げ込んで、あまりにも大きなギャップに、もう止めようかなとか思い始めていた。新宿でのニュースが流れていたが、赤坂の町は、新宿の出来事とは異世界のような歓楽街のままであった。何をしようと、何も変わりはしない。そして、何も起こらない。そんなことは誰もが知っていたように思う。 魯迅という中国の人が書いている。不満を両輪として正義の大道を突き進む(違ったかな・・・)と。自己を見詰め直すこと、問いかけること、そんな運動として始まったはずの戦いが、少しずつ形を変えて行った。学園祭の唐獅子牡丹のポスターが始まりであった。 全共闘運動と呼ばれた戦いは、内部対立や、先の見えない理論の世界で、次第に変質しつつあった。私は、授業もないので、毎日、働いていた(麻雀のためでもあったが)。働いていると、議論のためだけのような理論が嫌になってくる。最も鼻につくのは、「労働者、学生のため」というスローガンと、「民主化」という奇麗ごと。自分のため、親友のため、家族のためという固有名詞のためなら理解できるが、「労働者、学生」といった代名詞や、抽象的な概念を旗印にする運動は、どうにも嘘くさい。 しかし、自分達の感じた不満を表現しない限り何も始まりはしない。それは、自分自身に向けての戦いとして始まったはずなのに、いつのまにか、体制と反体制の戦いになり、体制へのアンチテーゼであるはずの運動が、反体制という旗印の下で組織化されて、ひとつの体制になって行くという矛盾を抱えていた。 私達デモの隊列は、砦に残る仲間達に声援を送りながら、正門へ向かった。その頃には、青い服の包囲網が完全に出来上がりつつあったことを、後にニュースで知った。当時は、それまでの戦いと同じように、どこかに逃げ道が確保できるという甘さがあったように思う。 正門を抜けて表通りに達した所で、青い服に一気に取り囲まれた。今日のところは、単なる排除ではすまないとは思っていた。一人一人が、ばらばらにされた。 私は、体格の良い2人に両側から腕をかかえてもちあげられた。足が地面を離れると、人間は力が出せない。3人目の青い服に、腹部を思い切り何発もなぐられた。そして放り出された。さすがにプロである。傷が残るようなことはしない。一着しか持っていなかった冬のコートは、殴られている間に、ボロボロに破れていた。 ボロボロにはなったが、幸いにして放り出されたので、私は近くの友人の下宿にころがりこんだ。今では、もう見なくなってしまった木造の下宿屋の2階。四畳半の部屋に、似たような友人が何人もころがりこんできた。運動そのものに限界を感じていたとしても、別の目的を持ち始めた組織に疑問を感じ初めていたとしても、誰もが、機動隊導入には我慢がならなかったのだ。自分達の責任を放棄して思考停止してしまった大学というものに、皆、腹を立てていた。 「正常化」というお題目を唱えながら、力によって問題を消し去ってしまおういうわけだ。目の前から邪魔物さえ居なくなれば、問題も消えてなくなると大学が考えた。東京大学が学問を放棄した。 砦は、次々に落ちて行った。最後に残った砦は、1日では落ちなかった。それで充分だったと思う。わずかの人数が武器も持たずに、自分達の旗を立てて国家を相手に戦い、2日間も砦を守ったのだ。(火炎瓶も武器と非難する人が居るかも知れないが、あの時には、誰も銃砲を使っていないし、刃物も使っていない。) あの運動が何であったのか、皆が何を求めたのか、それは時間の流れの中に置き忘れられて行くだろう。安田講堂の攻防は、歴史の一こまのような映像になりつつある。しかし、時には、抵抗という手段も必要だと思い出すかも知れない。 私は、どこかの組織に肩入れしていたわけではない。しかし、つい先日だったか、ふと若い頃の話しになった時に、元右翼と自称するOさんは、見事に当時の私の属していた色を言い当てた。自分ではまったく気づかなかったが、現在の私から推察できる程度に、私の人生に影響を与えたのかも知れない。 メランコリーと言えば角が立つ。肩肘はれば馬鹿である。誰もが、ふと苦笑いを浮かべて避ける話題だったようだ。
(当時の下宿屋さんといえば・・・この写真)
|
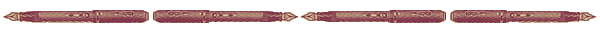 |


