


電話用魔法箱



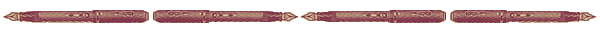 |
|
昔々のことじゃった。今じゃ大きゅうなった会社が、まだまだ小さかった頃のことじゃ。その頃、新しい電話会社がいくつもできはじめた。村人達は、どこの電話会社を使ったら、安い暮らしが出来るか、むつかしゅうてようわからんかった。まぁ、そげなことは、どうでもええことやった。 小さな会社の偉い社長さんは考えた。電話器に付ける小さな箱を只で配ろうと思った。この箱をくっつけると、一番安い電話会社を箱が勝手に選んでくれる便利なもんだ。村人は、只で箱をもらって電話代が安くなるから喜んだ。電話会社も、競争で安くした分の一部を戻すだけで、お客さんが増えるから喜んだ。そのわずかな差分を集めたら、そりゃぁーおっそろしいほど大きな商いになるちゅうわけだ。 その魔法の箱を、安ーく作って欲しいとオジサンは頼まれた。それが、偉い社長さんと初めて会った時じゃった。麻布十番の蕎麦屋だった。偉い社長さんは、腰が低い優しい人じゃった。オジサンは、ある小さな藩の番頭をしておった。 面白い話じゃったから、早速この魔法の箱を作りにかかった。手代の何人かが助けてくれたけど、藩からは冷たい目で見られておった。新しいことは嫌がられるものじゃ。 安く作らないと只では配れない。これが最大の問題じゃった。さらに、時々電話会社の料金が変わる。これを夜中の間に、村人が気付かないように書き換える特別な仕組みも難しかった。安い部品を集めて、魔法のように動く箱ができるまでには大変じゃった。ようやく試作品が完成して動いた時は、偉い社長さんも喜んでくれた。瓦版屋達も騒いだものじゃ。 話は、ここからじゃ。試作品ができたので、本格的な製品を作る試験と設計の見積りを頼まれた。藩の領主や、他の番頭が言うには、見積金額は1億円とか3億円だと言う。安くて小さな箱で、そんな設計費用はあまりにも高すぎる。オジサンは、もっと安くするように大反対をしたのじゃ。領主様は、これだけで儲けようと思っていたし、他の番頭達は、そんな新しい仕事はしたくなかったのだ。何を言っても聞いてもらえなかった。 あまりにも馬鹿馬鹿しい1億円という見積りを、オジサンは偉い社長さんとこへ持って行った。すごーく恥ずかしかった。職人として、こんなムチャクチャなものを見せたくなかった。見積もりを見た社長さんは、にっこりと微笑んで、すべての話は、ここで終わってしまった。 オジサンは、その時に自分の藩を見捨てた。試作品作りを手伝ってくれた手代達も、同じように、この藩を見捨てた。こんなとこに長居しても、ろくなことはないぞと思ったものじゃ。遠い遠い昔のことじゃ。
|
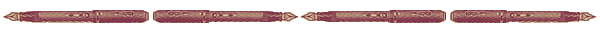 |


