


コンピュータはこわかった



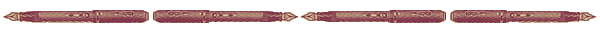 |
|
「コンピュータなんかこわくない」という本を書いたのは、レジャーの評論家として、原稿を書きまくっていた頃だ。そろそろ次の職業を考えないと、まずい状況だった。 企画の責任を追及されて、始末書を書くように言われていた。1億だか2億だか知らないが(20年以上昔の金額だから、そこそこ大きかったのだろうが)、その責任を、20代半ばの若造に押し付けて、皆でほおかぶりをするのかと思うと、どうにも腹立たしくて我慢ならなかった。これを拒否すれば、今の場所には居られなくなる。物書きで身を立てられたらいいなとか考えていた。 コンピュータには、興味があった。まだパソコンなんて登場する前だ。計算機を立ち上げるには、まずブートさせるためのプログラムを読み込ませる必要があった。ブートプログラムが入っていない計算機は、本当に、ただの箱である。スイッチを入れて、まずブート用のテープを読ませるまでの手順を、ON/OFFで入力しなければならない。そんな時代に、手のひらに乗る位のサイズ(今から考えたら巨大だが・・・)の論理素子が登場して、時代が変わると言われていた。 そんな時に、コンピュータの本を書かせてくれる出版社があるという。しかも、大手出版社で、新書のシリーズに加えてもらえることになった。まあ、当時のコンピュータの本の常であるが、2進法の計算から始めた。キープしたボトルの酒の量を、オンラインでつないで、全国で飲めるというチェーン店の紹介もした。自分達の名前では売れないから、有名教授の名前を借りて、「コンピュータなんかこわくない」という本を出版した。 本は売れなかった。シリーズの中でも、特に売れない部類だった。今、自分で読んでみても面白くない。頑張って、内容を面白くしたつもりだったのだが、文章が、あまりにも下手なのだ。今でも、文章はうまくない。でも、他人の文章を読んで、この人はうまいなぁと判る程度の経験は積んできたかも知れない。しかし、若者は、自分がそれなりの文章が書けると信じていた。山のように本を読んでいたし、評論も書いていた。だから、物書きの才能があるかも知れないという錯覚に陥っていたのだろう。他人に読んでもらうための文章は、意味を伝えるだけの文章とは違っていて、それには努力と才能がたっぷり必要だと気づいたのは、ずっとずっと後になってからだ。 しかし、大手出版社とのコネが出来た。これを使わない手はない。その出版社の入り口には、コンチキ号(もしかして知らない人が居るかも・・・イカダです)の大きな写真が飾ってあった。この写真が欲しくて、某有名人が欲しがっているという書類を偽造して手に入れてしまった。ごめんなさい。 その出版社を巻き込んで、赤道に沿って赤い糸を巻き付けようという計画を、最大手の広告代理店へ持ち込んだ。これをドキュメンタリにして、雑誌やテレビで取り上げないかという企画書である。これが成功すれば、私も当分は生活できるだろうし、しばらくは余裕ができるはずだった。現在のように、誰もが海外へ行く時代なら、赤道にも興味を引かれたかも知れない。しかし、海外旅行といえば、ハワイか、パリがすべての時代であった。営業活動の成果も空しく、「そういう秘境ものはね~」という程度の反応しか返ってこなかった。企業スポンサーも、みつけられなかった。 私は、それまでの職場に居辛くなって辞めた。物書きも駄目。企画書も失敗。先が何も見えなかった。その後、新聞のコラムを書かせてもらえるようにはなったが、それでは食べて行けなかった。それから何年後かに、コンピュータの世界で生きるようになるとは、想像もしていなかった。コンピュータは、自分の人生を変えるほど、こわいものだったのだ。しかし、その前に、ナイジェリアに出かけて人生観が変わった。 (コンピュータの歴史)
|
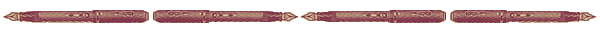 |


