


ハマターン



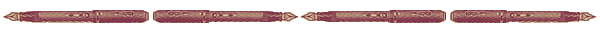 |
|
ハマターンの季節が始まろうとしていた。冬になると、サハラ砂漠に居座った冷たい高気圧から、西アフリカに向かって風が吹くようになる。 北から吹く風は、ナイジェリアの海岸部にもサハラ砂漠の砂を運んでくる。上空は黄色く染まり、赤い大地から吹き上げる砂ぼこりと一緒になって、指先も見えないような砂の濃霧をつくりあげる。冬の到来を告げる黄色い風を、ここの人々はハマターンと呼んでいる。 道を渡ろうとして、砂塵の中で方向を失った。手を伸ばした、その自分の手の先が、黄色い空気の中に消えてしまっている。濃密度な黄色の闇の中で、目が見えなくなったかのような恐怖を覚える。パニックになる寸前で、手を前へ伸ばしながら歩いた。手が何かに触れた。近くへ顔を寄せると、建物の壁であることがわかった。壁を手探りで歩きながら、1軒の家の玄関を見つけた。実体のあるものをみつけて、ほっとする。 私は一人で調査を続けていた。工業統計に従って、工場を訪問する。オヤジが、枠に詰めた湿らせた泥を、ペタっと地面に放り出す。再び、泥をつめてペタ、ペタッ。日干しレンガが作られて行く。窯業の工場だった。水車がまわっている。カタ~ンコト~ンと音を立てて、杵が打ち落とされる。穀物工場だった。そんな所に、自動車部品の工業団地を作ろうというのだ。ガラス工場があるから、ヘッドライトや窓が作れるはずだと高官が語る。ガラス工場を訪ねると、小さなガラス瓶が細々と作られていた。まあ、いいか。私の担当は、調査だから。 食事をする場所は、ホテルの食堂くらいだ。ホテルの前でボーイが車にひかれた。食事をしながら目をあげると、毎日、そこにそれがバラバラになって見える。誰も片づけない。最初、肉を食べる時には、一気に飲み込むしかなかった。しかし、そのうち慣れるものだ。そして風化して行く。 街にも食堂はある。出てくるのは、ウガリと呼ばれる芋の粉と、真っ赤なトウガラシのスープ。芋の粉をつまんで、スープにつけて食べる。州都を離れると、これしかない。新聞は地元の記事だけ。話し相手は居ない。持っていた本は1冊「戦争の犬達」(現場に居るかと思うと迫力はあった)。手紙は届かない。何通書いたかわからないくらいだが、1通も日本には届かなかった。もちろん、配達されて来ることはない。電話は、当然、どこにもつながらない。電話局で何度も何時間も待って試みてもらったことはあるが無駄な努力だった。テレックスも、首都のラゴスまで出なければ駄目だ。「金送れ」と首都から会社へテレックスしたことはある(無視された)。短波放送で何とか世界のニュースを聞きたいと思った。さすがBBCだと感心したが、日本の放送は雑音だけで聞き取れなかった。 ハマターンの季節になると、飛行機が何日も飛ばなくなる。飛行機が飛ぶのを見ると、外の世界と繋がっているという安心感が得られる。だから、外出したついでに空港を見たくなるのだが、飛行機の姿はない。 夜になると、お姫様達が、ホテルのまわりに集まって来る。エイズという言葉は聞かなかったが、ミドリザルの病気が人間に感染して、セックスで感染する治らない病気があるという噂が小声で広がっていた。何もすることはないから、カジノが開くまで、お姫様達とおしゃべりに出かける。はじめは、お客と思っていた彼女達も、すぐに話し相手だけだとわかると、おざなりになってしまった。 (*)夜中に外出するのは、それなりに危険なのだが、実際にお姫様と出かけた人の話しを聞いた。「どうだった?」「裸電球が1つあったよ」「それで?」「バケツに水が汲んであった」「なるほど」。 (*)目が覚めた時に、針金の入った頭が真っ暗なベットの隣にあったら恐い。・・・まだ、不治の病の危険を冒すほどには旅慣れていなかっただけの言い訳けざんす。 昼間、歩き回って帰って来る。鏡を見ると、そこには白髪の老人の顔がある。初めて見た時は、飛び上がらんばかりにびっくりした。突然、誰か別の人が目の前に立っているかと思ったのだ。鏡だと気づいて、おそるおそる覗き込む。しかし、やっぱり白髪なのだ。苦労をすると、一晩で白髪になると聞いたことがあったから、自分もそうなってしまったのかと思った。一旦、バスルームを出て考え込んでしまったほどだ。砂が全身を覆って、真っ白な髪と顔になっていたと気づくまでには、しばらく時間がかかった。 でも、実際に顔は黄色だったのかも知れない。その頃、毎日が眠くて仕方がなかった。旨いはずのビールを飲むと、ぶっ倒れるような苦痛に襲われた。以来、アルコールを受け付けなくなった。何年か後、病院で検査した時に、A型肝炎の抗体がありますねと言われた。強烈な眠さに襲われていた日々は、肝炎にやられていたのだろう。この地域は、マラリアの産地でもあった。マラリア蚊は、奇麗な水を好む。泥水のような所には住まない。ビアフラは、まわりにスワンプが広がっている。美しく透明な水だ。幸い、マラリアにはかからなかった。 このあたりで、高い建物はホテルしかない。遠くまで見渡せる。延々と、どこまでも緑のスワンプが広がっている。空は黄色だ。夜になると、遠くの石油ヤグラの炎が、ポツポツと暗い闇の中に見える。毎晩、ぼんやりと、それを眺めていた。 ホテルといっても町に1軒しかないわけだから、簡単に泊まれるわけではない(ホテルも、袖の下次第というわけだ)。部屋がなくて、プールサイドの更衣室に住んでいる人達も居た。一度、日本人が来て、更衣室を割り当てられたので、隣のベットにしばらく泊めてあげたことがある。彼は、アフリカの西側を一人で担当している大手自動車メーカーのサービスマンだった。私と同年輩の若者だった。彼は、さらに南へ旅を続けて行った。 ホテルの地下にカジノがあった。夜中に開くと、そこに通うのが日課になっていた。  
|
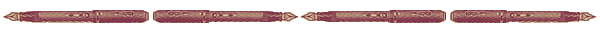 |


