


専門家ジャカルタに向かう



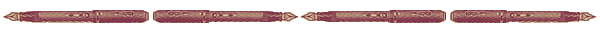 |
|
ジャカルタは、私にとっては青春の地に思える。この街について話し始めたら、いつまでも止まることがないだろう。あの街角、あの路地裏、屋台のお兄さん、友達、皆の顔が次々に浮かんでくる。長く住んでいる東京より土地勘があるかも知れない。そんなジャカルタの話しを始めてみよう。 ある日、青山の喫茶店で話していた。ジャカルタへ行きませんかという話しだった。話していたのは、以前は、雀荘の主とまで言われていたオジサンだった(私などより、すご腕だという評判を聞いていたから、尊敬の念を持っていた・・・男なんてそんなものよ)。仕事は、道路を作るために、交通の調査、解析をする仕事だと聞いた。 その頃は、調査の仕事をしていたが、道路の話しも、交通の話しも知らなかった(交通調査は、車の数を数えるくらいは知っていた)。本屋へ出かけて、交通関係の本を買い込んだ。コンピュータを使ってデータを解析するには、まずはプログラムができないといけない。コンピュータの本を書いたって、残念ながら、プログラムは書けない。FORTRAN入門という上下2巻の本を買った(例題と問題集の実に簡単な本だった。それ以上難しいものは読もうとしても分かるわけがなかった)。これだけでは不安だったから、コンピュータを知っていた友人に、サブルーチンなるものを、カードで作ってもらった(当時の大型コンピュータは、カードで動いていた)。これで準備万端整った(それ以上何ができるのか)。分厚い本を何冊もトランクに詰め込んで、私はジャカルタへ向かった。 インドネシアのガルーダ航空に乗って、バリ島経由である。バリ島は、まだ観光の島ではなかった。その年か翌年だったか、ようやくガタゴトの泥道が整備され始めたくらいだ。小さな空港がポツンとあった。延々と入国審査に並ばされた。 私は、交通の専門家として、ジャカルタに到着した。翌日、交通の仕事を一緒にすることになる2人の同僚に紹介された。他の分野の専門家や、仕事に誘ってくれたオジサンは居たが、とにかく、私を含めて3人で、交通調査・解析の仕事を完成させなければならない。1人は日本人のK氏、もう一人はスコットランドから来たF氏であった。皆、ほぼ同年輩、私がちょっと若かった。オフィスは、都心から少し離れた南区の、薬屋の2階にあった。今にも、崩れ落ちそうな鉄の骨組みだけの螺旋階段を登ったところがオフィスになっていた。荷物を持って登るのが、ちょっと恐いような、裸の螺旋階段だった。役所には比較的近かったし、当時、ジャカルタの南側にあったハリム国際空港にも近かった(今は、町の北西に近代設備の大きな国際空港ができている)。隣は、マーケットになっていて、夜になると、アセチレンランプの光があふれていた。 私達のミッションは、将来の交通量やパターンを予測して、ジャカルタの首都高速道路の路線や幅、ランプの位置などを決めるというものだ。将来の車の通行量がわかれば、どれ位の幅にすればいいかがわかる。ランプの位置が悪いと、渋滞を引き起こすし、不便である。この予測に基づいて、路線の設計が行われ、構造設計から、土地の買収、建設へと進んで行く。 (ここは解説です)日本の援助と長期資金で、ジャカルタに首都高を作る計画が始まったのだ。自国で建設資金を調達できない大きなプロジェクトには、海外の銀行から資金を調達する。日本にも、一般には知られていないが専門の銀行がある(預貯金を扱っているわけではない)。日本の名神高速道路は、世界銀行の資金で建設された(日本も貧しい時代があった)。借りた資金は、例えば道路なら、その有料道路の収入で返済する。もし、将来の交通を予測して、返済計画の目処が立たなければ、そこで可能性なし(アンフィジブル)という結論を出して終わり・・・というわけでもない。技術者には、可能性あり(フィジブル)にする対策が求められる。実際に道路ができれば、すぐに結果は目に見える。調査と予測から設計が始まる。 設計者からは、幅はどれくらいにすればいいか?、ここの交差点で右折する車は何台か?、ここにランプをつけても大丈夫か?、朝晩のピーク時間には何台位車が走るのか?、バス路線はどうするのか?などという質問が次々によせられる。それに対して、将来の予測値を答えなければならない。10年後、20年後、30年後の町がどうなっているかを考えなければならない。今は、車が走っていなくても、将来は豊かになって車社会になるはずだ。 (*)東京の首都高に対する不満を聞くと、あれを設計した人達を弁護したくなる。元々、首都高は片側3車線で設計されていた(現実は2車線しかない)。さらに、外側に環状線を作らなければならないことを、技術者達は知っていた(現実には、何もできていない。・・・今の外環状線よりも内側に計画されていた)。さらに、さらに、東京の外側には、方面別に大きなカープールを作って、そこから電車に乗り継ぐ計画もされていた。高速道路と連携する都心の一般道も、実に綿密に計画されていた(あれから30年以上たって、ようやく一部の計画が動き始めている)。そんなすべての計画を無視して、東京を混乱に導いた責任は誰にあるのか。それは、私の書く話しでもないだろう。しかし、心ある人達は悔しかっただろうと思う。 私達3人は、まず交通調査から始めることにして、どうやって調査するかの計画に取りかかった。皆、経験ある専門家である。私も、専門家の顔を維持するために、持ってきた本を、毎晩、遅くまで読んでいた。そこで仕入れた知識で、翌日の議論に臨む。さらに、解析方法も、知ったかぶりが必要だ。インドネシア政府の大型コンピュータセンターに案内されたが、こんなもの、どうやって使うかすら分からなかった。でも、パスワードが与えられた(今では、UNIXとPCになっているが、私のパスワードは生きていると聞いた)。 スコットランドから来たF氏が言った。私の町には、教会があちこちにある。教会は、高い建物だから、まわりが見渡せる。そこで、教会の上に、調査員が旗を持って登るんだよ。車が教会の前を通過したら旗をあげるんだ。さらに、次の教会でも旗が上がれば、車の通過経路がわかるという仕組みだよ。 ちょっと待ってくれよ。このジャカルタは、人口7百万以上の大都会だよ。見渡すこともできない。そんな方法は使えない。議論は続いた。 交通調査の方法から、その準備など、知らないことばかりなのだ。でも、そんな顔は見せられない。本の知識は、理論だけで実務は教えてくれない。丁度、1ヶ月ほど経った頃だったろうか。誰が最初に言ったのだろう。K氏だったようにも思う。 「今まで、この分野では、どこで仕事をされてきましたか」。うっ、と詰まってしまった。経験なんて何もない。本の山を担いでジャカルタまで来たのだから。 そして、皆、語り始めた。K氏は、ジャカルタに来る前は、営業マンだった。F氏は、スコットランドの役場に勤めていたのだと。私も、ど素人。大爆笑。1ヶ月間も、お互いに、経験を積んだ専門家の顔を続けていたわけだ。そうだったんですかという仲間意識の笑いの中で、ここに来る前の話しが続いた。皆、新しい仕事がやりたくて、ジャカルタへやって来た。全員が、毎晩、部屋に帰って必死に本を読んでいたのを知った。 ひとしきり大笑いが続いたところで、お互いに顔を見合わせて凍りついた。「どうしようか」。仕事は始まってしまっているのだ。仕上げるまでは、帰れない。当然、納期だってある。現実がどうであれ、我々3人は、インドネシアに派遣された交通専門家なのだ。専門家としての回答が求められている。それから、ドタバタ劇が始まった。 (*)ジャカルタに関わって、気づいたら約10年。いつもトランクが、私の身近にあった。数ヶ月単位で往復しているのだが、東京とジャカルタの生活が、自分の中では個別に連続したものに感じてくる。2~3ヶ月ぶりに東京に戻って来ても、その期間がすっぽり消えて、昨日も東京に居たと思う。ジャカルタに着いても同じこと。2つの生活が並行して動いているのに、片方に居ると、もう一方の生活をすっかり忘れるようになる。合計すると、ジャカルタに居たのは4年くらいになるように思う。 今では、K氏は、国際機関に居て、その分野の専門家として名が通っている。F氏も、あちこちから頼られる専門家だ。私も、いつのまにか専門家と言われるようになってしまった。専門家という言葉を聞くと、あの日の、爆笑のあとで凍りついた瞬間と、その後のドタバタ劇を思い出してしまう。
|
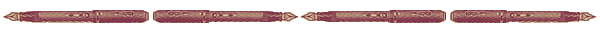 |


