


ハサック



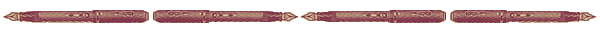 |
|
先日、友人がオフィスへ訪ねて来た。自転車を担いで入ってきた友人を見て、「変わったお友達が多いんですね」と言われた。昔々、彼を含めて男達3人で暮らしていた頃がある。表札には「ハサック」と書いてあった。「ハサック」とは、ペルシャ語で南京虫のことである。 当時、皆、学生としての籍は持っていた。しかし、同時に仕事もしていた。どうせなら、自分達で会社でも作れないかと思った。まずは事務所を借りようということになった。高級マンションを借りた。しかし、自分達の暮らしを維持しながら事務所を維持できるほどの甲斐性があるわけもなかった。結果、その借りたマンションに住み始めることになった。学生とはいっても、少しは働いてサラリーマン並みの収入がある男達が3人分だから、普通の若者には住めない程度の高級マンションである。一人一部屋で、台所と洗面所、浴室が共通だ。 先日訪ねて来た友人Mは、美術系の大学に通っていた。その大学の教授が、丁度真下の階下に住んでいた。教え子達が、真上の階で騒ぎまくり、間違ったふりをしながら、階下のドアをたたきまくるのに耐えかねたのかどうかは知らないが、まもなく、その教授は引っ越して行った。 私は、技術系の大学なので、当時は女学生などには、ほとんどお目にかかれなかった。そこで、友人Mの大学のゼミ旅行があると、参加することにしていた。ほとんどが女学生というのが、とても魅力的である。階下に教授が住んでいたのだから、ニセ学生の素性はばれていたと思うが、お目こぼししてもらうことができた。良い時代だったのかも知れない。 もう1人は、ドキュメンタリに出演した主人公。これが実に真面目で豪傑の薩摩男子である。他の男達が、女の子と部屋に居たとしても、お話をしているだけだと信じている(まあ、そうなんですけどね・・・)。お茶が入ると、部屋まで持ってきてくれる親切なところがあって・・・、う~ん、なんですね。 若いむさくるしい正体不明の男が3人で住んでいて、変な格好の若者が何人も出入りしたり泊ったりしているとなると、当然、疑われる。当時は、学生運動がますます過激になりつつある時代だった。いつも、いかつい目付きの人達が、私達のマンションを見張っていた。 何故「ハサック」かと言うと、私以外の2人は、アフガニスタンに、はまりこんでいたからだ。アフガニスタンの奥地は、まだまだ秘境であった。彼らは、その奥地に惚れ込んでいた。そこで使われる言葉から、「南京虫」が選ばれることになった。その後、某国が占領していた当時も、パキスタン国境から近づく方法を、彼らは知っていた。今でも、この地域の情報に関しては、Mなどは一流だろう。 入り口には、ドラム缶のような箱を置いていた。宿泊者には、なにがしかの寄付を要求する寄進箱であった。しかし、お金が入ったことはほとんどない。私は、真っ赤な車にワイドタイヤをつけて、排気管の音を良くして、車高を低くして走りまわっていた。首都高は、何分で一周できるかが楽しい遊び場であった。だから、今でも、そんな若者に出会うと、つい微笑ましくなってしまう。しかし、つるんで走る連中は好きではない。リスクは一人で負えと言いたい。Mは、S6と呼ばれるオープンカーに乗っていた。東名高速を走っている最中に、動力を伝えるシャフトが折れた時は、さすがに驚いた(すごい音がしますよ)。Mと一緒に車で、銀座の夜がはねる頃に、お姉さんを送りに出かけて御小遣いをもらったりしていた。その頃から、いいかげんな生活に浸り込んでいったのかも知れない。大会社に勤めていながら、「ハサック」で泊まっているうちに、我々を見て、会社勤めが嫌になって人生を狂わせた友達も居る。 なんとなく解散したのは、多分、食べ物の恨みではなかったかと感じている。共有の冷蔵庫に食べ物を買っておくと、誰か食べてしまったりする。食事をしようとすると、空っぽだったりする。こういうのが重なると、どこか不信感がつのり始める。食べ物の恨みは、やっぱりたまる。まあ他にも、集めた部屋代を使いこんだりする事件もあったりしたのだが。しかし、同じ釜の飯を食べた仲間というのは、やはり親友である。 居候しているうちに、普通の会社員では居られなくなった友人も、今では、すっかりオジサンだ。あの頃の、銀座のお姉さん達も、オバサンしてるだろうなぁ。あの人をモロッコで見かけたよという風の噂も聞いた。ゴアの刑務所から本を送って欲しいと便りを寄越した彼は、その後亡くなったそうだ。しばらく南米に消えていた彼女は、普通に仕事をしていたかと思うと、突然風のように居なくなる。今では大学教授の顔をしている男が、その頃は競輪の予想屋だったりした。そのうち、そんな皆の話しも書いてみよう。
|
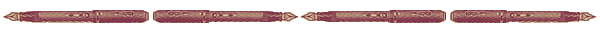 |


