


楕円を削る



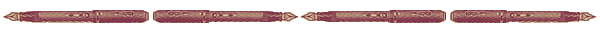 |
|
旋盤という機械を御存知だろうか。材料をまわしながら、刃物を押し当てて削り出して行く工作機械である。材料は高速で回転しているから、刃先を横から押し当てると、その部分は、円筒形に削れることになる。さて、その旋盤で楕円形の円筒を作りたいという話しがあった。 ジャカルタでの仕事がひと区切りついて、次は何をしようかと考え始めていた。悩んでみたところで、なかなか結論なんか出ない。そんな時は、原点に戻ってみようなんて、まともなことを考えた。卒業以来、自分の専門とはかけ離れた世界を歩いて来た。それでは、一度、学会にでも行ってみるかと思った。ミュンヘンで、国際学会が開かれる。ドイツへ向かった。 楕円形の円筒を削る工作機械の話しが持ち込まれたのは、丁度、そんな気分になりかけていた頃であった。これが、なかなか難しい。難しいとなると、やってみたくなる。アイデアは既にあった。旋盤に取り付けた円筒が回転するのに合わせて、刃先を前後すればいいだけだ。1回転するあいだに、刃先が1往復すれば、その振幅分の楕円形になる。アイデアは単純でも、実現するとなると、超高速で刃先を制御する仕組みを作らなければならない。 刃先を超高速で前後させるための仕組みは(実は圧電素子を使うのだ・・・もう特許が取られているはずだから書いてもいいだろう)、T大学S研究所のH教授が発表していた。ところが、この教授とは、ミュンヘンで一緒だったのだ。ミュンヘンからパリまで、旨い店を探して、あちこち歩き回っていた。スイスでは、フォンデュ~はどこだと叫びながら、夜中まで町中を歩き回ったりしていた。 仕事の依頼主と一緒に、研究所まで会いに出かけた。「えっ!。誰が来るのかと思っていたら、あなたでしたか」とH教授は驚いた。それまで、私は遊び人として知られていたわけか(?)。 工作機械の開発は、その前にも1つ手がけていたが、それは大失敗に終わっていた。コンピュータのソフトウェアはわかっているつもりでいても、ハードウェアの開発となるとまったく別物である。理論通りになかなか動いてくれない。論理的に解決したつもりでも、ノイズや安定性など、経験の積み上げが数多く必要になる。思ったように「動作する」ことと、「動作し続ける」こととは、とてつもなく大きな開きがあるのを知った。前回の失敗作は、3分間は動作したのだ(失敗した客先の皆様、本当にごめんなさい。深く深く反省しております)。 当時のCPUの速度では、刃先の動作を制御することと、前後の振幅の制御を同時に行うことは不可能であった。CPUを2個使うことになった。ハードウェアの制御には簡単な4ビットCPUを組み合わせるか、せいぜい8ビットのCPUが1個というのが主流であった時代に、16ビット系のCPUを2個使うというのは、それなりに画期的なことではあった。マルチタスクで動かすために、OSを入れることにした。アセンブラでのプログラムではなくて、OS付きのボードに簡単な言語を開発することにした。 いつまでも思ったように動かすことが出来なくて、ひたすら客先で頭を下げ続けていた記憶だけが残っている。会議室にずらりと並んだ、客先の人達の前で、次々に出される問題点と納期遅れの指摘を受けながら、「早く会議時間が過ぎ去って行ってくれ~」と願いながら座っていた。だが、客先の人達も全員技術者である。だから、こちらの苦しさは、すべてわかっている。公式の場だから、強い言葉も出るし、クレームも多くなる。しかし、会議の場を離れると、「ここの所は、こうやって解決したらどうですか」「この問題の原因は、このあたりにありそうだと調べておきました。これがデータです」と教えてくれる。そんなアドバイスに、どれほど助けられたことか。 かくて、楕円形の円筒を削る機械は完成した。製品の発表会は、大々的に行われた。日本を代表する産業の重要な製品を作るための機械であったから、「これは、儲かるぞ~」と喜んだ。ところが結果は少々違っていた。機械は良かった。しかし、高性能であり過ぎた。すぐに需要を満足してしまった。儲からなかった。 こうした機械が、当時は高級品の生産に使われていたが、今では、誰もが買える製品に使われるようになっている。誰もが「まさか、楕円形だなんて」と思うようなものである。わずかな楕円になっているのがポイントなのだが、ほとんど誰も知らないだろうなぁと思いつつ自己満足にひたっているのである。
|
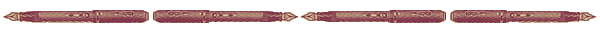 |


