


大臣の女を捜せ



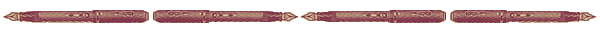 |
|
仕事の契約が、吹き飛んだ。それは、ポートハーコートへ着いてからだ。 契約書を取り交わすために役所へ出かけた。大臣に面会して、仕事の話しを始める段階になった。彼は、そんな話しは聞いてないと言った。私は、メンバーの中でも、最年少の方であった。ここまで来たのは何のためだったのか。様々な会社から何人ものスタッフが、あるプロジェクトのために、アフリカのはずれまで来たのだ。どの会社にとっても大打撃である。交渉は何日も続いた。いつまで経っても、契約は進展しなかった。毎日、役所の階段を登った。この階段の段差が、全部違っていて、しかも傾いている。階段の段差が同じだという感覚に慣れていると、登るのが意外に大変である。 役所の前は、マーケットだった。マーケットの入り口近くは、食料品。奥へ入って行くと、テントをはった店に、衣料品が並ぶ。値段が高いものほど、マーケットの奥というルールがあるかのようだ。ごみごみした路地のにおいは、アジアのにおいとは全く異質だ。こんなことを書くと、誰かに怒られそうだが、動物園の肉食獣の檻を想像してもらえると良い。食べ物の違いは、においにも現れる。アフリカンマミー達の明るい声が響く(この明るさは好きだ。ケニアの話しをする時にでも書くつもりだ)。 町のレストランといえば、2~3軒しかなかった。そのうちの1軒は、泊まっているホテル。もう1軒は、うす暗い中華料理屋。われわれが行くと、必ず青江美奈のテープが流された。そこの親父は中国人で、東京の四谷で店を持っていたことがあると話していたが、それ以上は、口を閉ざして何も語ろうとしなかった。青江美奈のけだるい歌が、この親父と何か関係があることまではわかったが、日本を離れて、自分の国にも帰らずに、ここまで流れてきた老齢の男には、それなりの事情があったのだろう。アフリカは、そんなものも、すべて包み込んでくれる母なる大地だと感じることがある。 対策会議がもたれた。このままでは、赤字がかさむばかりである。一部のメンバーは、帰国することになった。交渉は続いていた。残ったメンバーは、ボスと私を含めて4人ほどではなかったろうか。 我々のボスが新しい手を考えた。クレームレターを作ろうじゃないか。なるべく、もっともらしいのが良いだろう。日本の大臣が、貴国の対応を憂いているという内容にしようと決まった。ナイジェリアは、軍事政権の連邦制だった。連邦というのは、国家の集まりでもある。我々は、州政府を相手にしていたから、国家と国家の話しにしてしまおうということになった(そろそろ時効だろう・・・これはフィクションです)。丁度、ボスの名前と、日本の首相の名前が一緒だったから、ボスを首相の弟にすることにした(「てめ~、ウチの弟と、ちゃんと話しつけたれや」・・・という内容の手紙が完成した)。レターヘッドを印刷し(たった1枚のためにも印刷するという芸の細かさ)、クレームレターを作成し(そうだ、あの時タイプライターを持っていたのは、私だった)、サインから紋章まで、いかにも権威がありそうなレターが完成した。 このレターを持って、交渉が始まった。しかし、日本の権威は、役に立たなかった。当時は、日本の車も見かけなかったし、電化製品も入ってきてはいなかった。日本なんて、どこにあるのかも知らない人達ばかりなのだ。エチオピアの隣りあたりだと思われていた(エチオピアは美人の国だと思われているから、まあ、その隣りなら悪くはない)。戦前派のボスは、日本の艦隊が、ここまで来ていたら良かったのにとわめいていた(日本の南雲艦隊はセイロンまでだ)。 どうにも交渉が行き詰まっていた頃、エベル君から願ってもない情報が手に入った。町のタクシーを取り仕切っている雲助の大ボスの元には、多くの情報が入ってくる。大臣には囲っている女が居るらしいというのだ。町の雲助達に指令がまわった。まもなく彼女の家がみつかった。このあたりのほとんどの家が、細い木で回りを囲った小屋のような家であった中で、彼女の家は、モルタルのような造りで、いかにも立派に見えた。 当時、石油の価格が一気に上昇し、オイルマネーがあふれていた。毎朝、小屋のような家から、赤い土の道へ通勤者の群れが吐き出されるのであるが、男達は、びしっとスーツを着込み、女達もパリの最新ファッションを身につけている。手に持っているバックは、日本でもお目にかからなかったようなルイビュトンだったりする。赤い土煙りの舞う道、丸い木の小屋、スワンプの広がる大地の中で、何か異様な感じがしていた。時々、靴をふくために、立ち止まってハンカチを出すのだが、2~3歩けば、土煙の中だ。 運転手による張り込みの結果、大臣の来る日が特定できた。我々は、彼女の家へ向かった。大臣は、契約書にサインした。 (*)数年前、訃報が届いた。この時のボスが、バンクーバ空港で日本への便に搭乗しようとしていた時に倒れて、そのまま亡くなったという知らせだった。世界を渡り歩いていた彼が、日本で落ち着いて暮らすために、丁度住んでいたカナダの家も引き払って、帰国しようとしていたところだったのだ。彼は、いつも私のことをチャン付けで呼んでいた。「アリチャン、元気かい。少しはまともな生活してるかい。」と言いながら、にっこり笑顔を見せる。話しだけは、合理的なビジネスなのだが、実際の生き方は、義理と人情の浪花節。誰かが困っていれば、仕事や自分のことなんか、そっちのけで駆けつける。自分が、どんなに苦しい時でも、飯を食わせてくれた(だから、つい真似をしたくなる・・・)。浪花節の男達には、ビジネスは向いていないのかも知れない。苦しい時には、いつも彼の笑顔を思い出す。彼は、最期まで旅を続けた。家族は大変だっただろうが、幸せな人生だったと思う。今も彼が始めた小さな農園がアフリカにあるはずだ。黙祷。 (*)一緒に居た別の一人は、マニラでタクシー会社をやっていると風の便りに聞いた。  
|
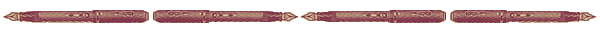 |


