


札束と銃殺の恐怖



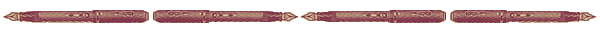 |
|
契約書にサインが得られた。 契約が成立して、我々はお金を受け取ることになった。仕事は始まっていなかったが、受け取るものは早く受け取れるほど嬉しい。州政府の中央銀行へ出かける。がっしりした建物の銀行は、天井も高い。頭取が、銀行の業務時間が終了するまで待って欲しいと言う。我々は待った。 業務時間が終了して、客は誰も居なくなった。お金の準備が始まっていた。しばらくして、中央銀行の大きな金庫の扉が開かれた。分厚くて巨大な扉が開いたのだ。高い天井の広い部屋で、向こうの壁にある大金庫の扉を、じっとみつめていた。そこから、台車が出てきた。台車の上には、人の背丈よりも高く、札束が積み上げられていた。3~4人の男達が、札束の山を支えながら、静かに台車が進んでくる。オイルマネーの交換レートは、非常に高かった。 我々は、全員のスーツケースを空にして持って来ていた。札束を、スーツケースに次々に詰め込んだ。いくつものスーツケースにびっしり詰め込んでも足りなくて、手に持っていたスーツケースにも、札束があふれていた。 ホテルに帰った我々は、これをスイートルームのツインになったダブルベットに投げ出した。中央銀行の帯封をした札束は、すべて新しい。手が切れるような札束が、ベットの上にあふれていた。札束の山に埋もれて、皆で歓声をあげた。札束の中にもぐりこんで、はしゃぎまくった。札束を投げ付け合いながら、歓声を上げ続けていた。 その時、親しいドイツ人が部屋に訪ねて来た。その光景を見て、彼は、真っ青になって叫んだ。「こんなのをホテルの人間に見られたら、お前ら全員殺されるぞ」。確かに、その通りであった。ホテルのボーイにでも見られたら、従業員が全員で襲って来るだろう。そして、誰も居なくなったで終わりである。しぶしぶ、我々は、札束のベットで戯れるのは諦めた。 しかし、我々が契約を勝ち取って、大金を手に入れたという噂は、そのドイツ人から、外人達の間へは広まって行った。それまで「アフリカは、ヨーロッパ人のものだ。お前らは、アジアに居ればいいんだ」と、面と向かっても罵声を浴びせていたヨーロッパ人達が、一目置くようになったのが分かった。対応の仕方が、がらりと変わって、友達顔をするようになったのだ。 しかし、この金は、すべてが自分達のものというわけではなかった。キックバックが必要だったからだ。その配布が始まった。 ここでは、家族の誰かにお金が入ると、同僚や親類縁者が集まってきて、おこぼれにあずかろうとする。ここでは、家族は大家族である。だから、お金を受け取ったことは、同僚に知られたくないのはもちろんのこと、妻にも知られたくはない。近所の人間にも知られたくはない。 単独会見をするのは、夜しかない。夜、自宅を訪問して、家族が居ない場所で、金の受け渡しをする。当時のトランクは、サムソナイトなんかじゃなくて、いわゆるジュラルミンのトランクだった。これに札束を詰めて運ぶ(例の事件が日本で起きた時、日本も同じじゃないかと懐かしかった)。 ボスと私は、エベル君の車に乗って、関係閣僚の家へ向かった。戒厳令下では、夜の道に、治安維持の軍隊が出ている。当時、贈収賄は銃殺刑であった。実際に、銃殺されたというニュースも伝えられていた。軍事政権というのは、成立当初は潔癖な理想を追求するものだ。町では袖の下が通用しても、理想を求める軍隊と話しをつけるのは難しい。特に、軍事革命直後は、そうである。まさに、軍事革命直後であった。 車の後部座席に身を伏せて、外から見えないことと、軍隊に停止を命じられないことを祈りながら、毎晩1軒づづ、お金を配って行った。夜、遅い時間に出かけて、外出禁止令の時間までには戻らなければならない。正直なところ恐かった。 一人でオフィスへ出かけたこともある。内密な話しがあると言えば、秘書を部屋の外へ追い出す。アタッシュケースから札束を出す。何も言わずに、すぐにしまおうとする。「ところで俺の取り分はないのかい」と言ってみる。すると、すぐに、1~2個の札束が返って来る。これが私の取り分というわけだ。意外にたまった。 残っていたメンバーは、私を残して、一旦、日本へ帰って行った。プロジェクトチームを再編するためだ。かくて私は、人質として残された。しかし、成功報酬分、仕事のために預かった金、内緒でキックバックからキックバックさせた金、相当な金額が札束になって手元に残っていた。 かくて、ルーレット台は回る。象牙の玉が、カラカラと走る。盤面の数字の並びは、すっかり頭の中に入っていた。
|
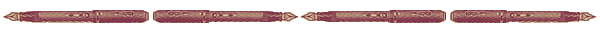 |


